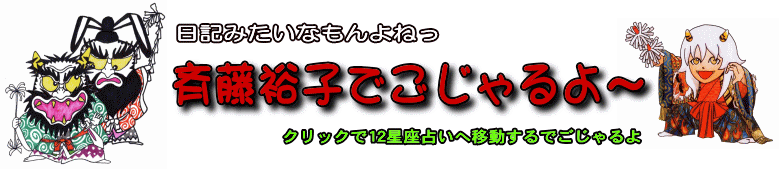『続いて矢旗です。誉田別命は、渡 哲也さんです!』と。
一瞬シーンのザワザワ、クスクス。
『はっ
手元の資料には、“渡 勇さん”と、ちゃんと書いてあったのですが。
あーあ
二神(従者)の園田哲也さんと混ぜ混ぜになったものと思われます。
しかしながら!!
一部のファンの間では、渡さんと園田さんの副団長・同級生コンビが神のコンビを組む時には『今日は、渡 哲也コンビなんじゃね~』などと、実際に表現されているそうです。
・・・まぁ、何言っても言い訳だな~
今年4月の吉和競演は大江山ですが、以降の競演は矢旗になりそうです。
配役を大幅に変え、タイトルを狙います。


41歳、同級生コンビ。

多くの神楽団が保持している定番・人気演目ですが、ここでは上河内の滝夜叉を堪能してください。というご紹介です。



この日の結びです。
皆さんから多くの支持を得る大江山だからこそ、いつものメンバーで、いつも通りに舞いました。


いろんな都合があるのですが、拝見できて嬉しかったです。
三谷神楽団の打ち上げには、褒め言葉がありません。
ダメ出しキャッチボール。
しかもそのボールは、どこから誰に投げられるか分からないので、注意が必要です。
自分に飛んできたら素早く、誰かに回さなくては身が持ちません。
傍で聞いているとヒヤリドキリとするやりとりですが。
これも三谷の宮から始まり、三谷の宮へ帰ってくる、団員の皆さんの伝統なのかな、と思います。


中川康弘さんとは先輩・後輩のふかーーーい関係

『えー皆様、盛り上がってますか?』
『見えん見えん

2012,03,24 Sat 13:15

この日の朝、今年初めての鶯の声を聞きました。
『ケッキョン、ケキョン』とまだあどけない。
3回目を迎える弥生の神楽交流会。
春到来に、安堵の和やかな笑いが響きます。
本格的な競演シーズンの幕開けを前に、地元のみなさんに「今シーズンも頑張ってきます!」と意気込みを語る、熱い舞台です。


競演大会で優勝した実績もあります。
15年前ごろ現在の形に整えて舞い始めました。
奉納ではお馴染みの演目です。


実はその時習得したもう一つ別の演目が、たんすの中に仕舞われているそ
うです。
若手・新人が入団すると、まず、頼政の神を演じることが決まっています。
そうして、秋の奉納などで氏子の皆さんに披露します。
今回は市田直己さんと、初めて神を舞う齊藤由喜美さんのお二人でした。
あまり他の地域に持って出ることのない演目です。


紅白餅やら、コウタケ入りやら色々
様々な大会でよく顔を合わせる両団。
新舞・旧舞の枠を超えて、お互いに刺激し合い、高め合うお付き合いです。
新編・伊吹山(1演目目)
日本武尊の武勇伝を描く、3段完結編となります。
戦いに明け暮れた生涯の終わりに、妻・弟橘姫との永久の契りが結ばれます。
生では得られなかったものを、死でやっと得ることができたんですね・・・。

武尊の最後の相手に相応しく、威風堂々とかっこいい。

打ち上げまで道のりが長いので、続く!
2012,03,23 Fri 21:28

遠目に見ると可愛い。

無理と思いつつ、この2日間自分なりにもがいてみましたが、やっぱり無理!
観念して、電気屋さんに来てもらうと、2分で、全て解決しました。
『全然たいしたことじゃなかったんで、お代はいいです!(爽やか~)』
はあ、それはどうも・・あはは、は・・・
情けないけど、お手上げですね。
遅ればせながら『上田宗箇の世界展』へ行きました。
茶碗から始まる茶道具、和風堂から庭園まで広がる「武将茶人のウツクシキ」です。
展示室内に再現されたお茶室は、見事!
とにかくご婦人方を中心に混雑しておりました。
「宗箇は豊臣秀吉の側近で多くの武勲をあげ、戦場で名を馳せた優れた武将であった」
大阪夏の陣で着用した「緋地立波文陣羽織」。
モダンで大胆なデザインを見ると、その人となりがなんとなく想像できる。
焦げた跡も生々しい。
又、大阪夏の陣で、急迫する敵を待ち受けながら竹藪で作ったという「敵がくれの茶杓」も、物言わぬ迫力があり印象的です。
明日をもしれぬ戦国で。
“静”と“動”の対極を重りにして、宗箇という重心が安定するヤジロベエのようなものでしょうか。
めくるめく展示ですが、焼き物が好きな方にもおすすめです。
あと3日なんだけど。ぜひ
上田宗箇 武将茶人の世界展・詳細
http://www.hiroshima-museum.jp/special_top

2012,03,23 Fri 00:27
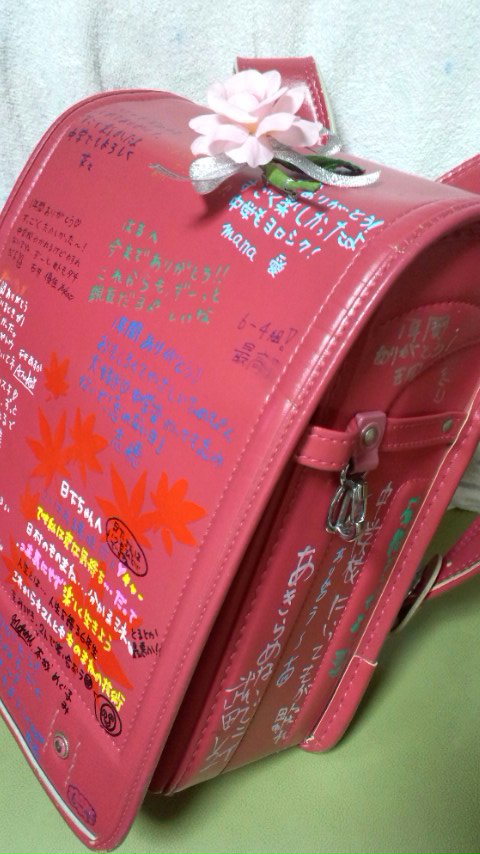
この日のためにかなり苦戦した手作りのコサージュ。
クリーニング済のピカピカな制服と、汚れて穴だらけの愛着のある上靴。
第40回卒業式。
卒業生145人は、うれし涙いっぱいでした。
私がずっと、誰かのおじいちゃんだと思っていたのは、実は校長先生
穏やかな、よく通る声の贈る言葉。
『夢に大小はありません。人と比較する必要もありません。
夢を叶えるのは底力です。
その底力を養うのは楽しい事・苦しい事を含む、全ての経験です。』
『皆さんと一緒に卒業できて幸せです。ありがとう。』
校長先生もこの春定年。挨拶の途中、涙に変わりました。
娘は6年間通して、素敵な先生に恵まれました。
特に最後の担任の先生は、
『“良い子”だけではダメなんです。気が利く・賢い、社会から必要とされる応用力を養っていきます。』
数年先を見据えての教育方針に、深く共感しました。
それにしてもよく叱られました。
でも、よく褒めてもらいました。
ついでに私もよく叱られたし、一緒に泣いてもらった。
「沢山の人=視点で拘わってもらい、育ててもらうことが大切」だと、やっと実感しつつある。
濃い6年だったと思います。
本当に!お世話になりました
2012,03,19 Mon 23:00


右上:あさひが丘神楽団・下田敏則さん
左下:中川戸神楽団・香川紗輝さん
右下:下五原神楽団・升本隆さん(随身丸さんだよっ)
左上:鈴張神楽団・橋原慎也さん(手伝いではありません
(しょうもんき・しんのうせんげ)
『昨年の初上演から、5回目の上演となりました。
やっと個々の役柄に、自分の演じるものが見えてきたころだと思う。
この演目の魅力を伝えられるのは、いよいよこれからが本番でしょう。』
夏本秀典団長のお話です。


初見だった方は楽しみにされていたでしょう!
この演目もまた、勧善懲悪とは一味違い、重太郎の業と因縁を描く物語です。
弟の重蔵を亡くした重太郎の叫びがダイレクトに届いて、印象に残りました。


その目に何を映してきたかを思うと、悲しさばかりです。
秋の奉納神楽ではとりを取る、一二神祇の中で最も勇壮な舞です。
荒ぶる神・荒平と太夫の問答には、榊や米などの由来、効力、神仏との関わりなどが説かれます。
その終わりには荒平は良き神となることから、昔の方が神楽に込められた思いが、時を超えて蘇るような気がします。

彩心さんの軟かな声が会場に響きます。

およそ20年前新舞を取り入れる際、初めて取り組んだのが土蜘蛛で、思い入れが強い演目です。
今回、胡蝶を演じたのは中学生の塩崎 樹(いつき)さん。
『えーっ
小太鼓の山田悠人さんも中学生。
両立を応援しています!

下田さんのアイデアが活かされた幕を準備しています。


来年は、3月10日(日)の予定です。
2012,03,17 Sat 20:32