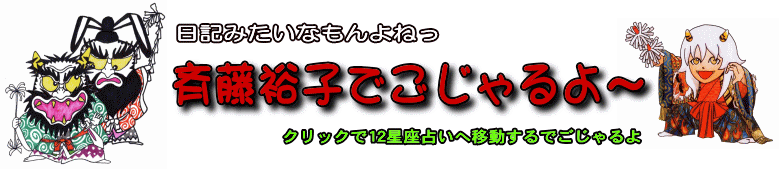スーツにハイヒールで出かける後ろ姿を頼もしく見送りました。
18歳だし、もう親の出番はないと思っていましたが。
最近では“最後の入学式”という考え方で、大学の入学式等も保護者の出席が増えているようですね。
卒業式には行こうかな
それにしても、今日の雨には影響を受けた方も多かったでしょう。
しばらく寒そうなので風邪に気を付けましょう

終盤に入ってきました~。
~第十幕 三鬼 山代白羽神楽保存会 北中山子ども神楽団~
前回拝見した際に「なんて面白い神楽
今回もとても楽しみにしていました。
人の心に湧く欲望を鬼に例え、その鬼の手強さに悩まされながら。
希望と意欲を持って、なんとか目標を達成することが出来る。
しかし、人の心に欲望や怠け心は決して無くならないのですね。
目に見えないものを舞うんですよねぇ、神楽は。。。
なんと人間らしい、しみじみとよく出来ている(何度も言っていますが)天蓋の下で舞うにふさわしい神楽だな~と感心しりきなのです。
加えて、子供たちの可愛らしさと愛嬌は抜群です。
北中山子ども神楽は、現在5歳から14歳の13名の子供たちが山代白羽神楽保存会の皆さんから指導を受けています。
衣装の一部は手作り等、保護者や地元の皆さんの協力の中でスクスク育つ子供たち。
神楽の原点を見るような気がします。
〇流れ〇
ある目標を達成しようとする大夫と、その心の闇に隠れた欲望が争うという悪魔払いの舞。
目標を達成する途中、様々な誘惑にかられ、一時的な快楽を求めてしまう気持ちを鬼に例える。
大夫はその欲望である鬼と戦い、最後には打ち勝つことが出来る。
その後は、より強い思いを持ち目標を叶えることが出来るという、人間の心の問答を神楽化したもの。
目標となる的を月に例えたり、取り組もうとする意欲を弓に見立てるなどそれぞれに意味深い意味合いが込められている。
今回は、山代白羽神楽の伝承の舞に一味加え、北中山子供神楽も出演し、可愛らしさや子供神楽ならではの表情をご覧ください。







大鬼小鬼の演目にこのあたりの雰囲気が似ていますね。







2018,04,06 Fri 19:33
ご来場有難うございました。
出演は琴庄神楽団の皆さん、賑やかで心から楽しい初日公演となりました
皆様今朝は、記念の紅白モチを食べられましたか?

12月まで全38公演、そしてあと37回公演。
毎週水曜日、大好きな神楽でお逢いしましょう。

全幕の長刀舞に続き、力強く緊張感のある舞です。
「阿戸神楽といえば“八花”」というイメージがあり、公演依頼も八花が多く、今回の五刀はこれまであまり大きな舞台で披露される機会がなかった舞です。
~第九幕 五刀 阿戸神楽団~
武芸の達人による柔術の型を取り入れ発展してきた、阿戸神楽の持つ迫力です!
2本を結び付けた刀はまさかの長さで、前後左右・高低に目を配りながら舞われます。
激しい動きの中に繊細で大胆な技が駆使され、途中、1本の小刀を口にくわえてからは呼吸も難しく、いよいよ集中力が必要となります。
昔は、刃が入ったものを使用されていたと伺い・・・絶句。
神に奉納される舞は、それくらい真剣に行われ。
その役割を担う舞子さんは地域のヒーローであったと想像します。
〇流れ〇
舞役はひとり。はじめ左右に2本(4本)の刀を持って舞います。
そして最高潮に達すると、更にもう一本小刀を口にくわえ、計5本の刀を身に帯びて激しく舞い回ります。
小刀を口にくわえた状態で前回りするなど、極めてアクロバティックな演技が見所です。神に仕える武人が持つという五刀の威力を湛える舞です。
前転する場面は、ドキドキ興奮して見入っていたので、カメラで撮るの忘れました











今回も色んなお話をしてくださったのは、代表の岩森憲雄さん。
話を聞いてから見るのは、面白さ倍増ですね
2018,04,05 Thu 12:52

桜をゆっくり眺められる年はありません。
今日は桜吹雪の中の花見を楽しむ人が多かったですね。
花びらも一緒に食べるお弁当
この後、瑞々しい若葉に変わる様子も楽しみですね。

~第八幕 長刀(なぎなた)舞 石内神楽団~
1本の長刀を持つひとりの舞子さん。
長刀を操る緊張感と気迫が伝わってきて、見る側も血が騒ぎます。
時折、手の汗を衣装で拭う姿がリアル。
観衆と心がひとつになる人気演目で、まつりでも、フィナーレの関舞の前に舞われることが多いそうです。
上演後は控室で、長刀の長さと重さに新ためて感心しました。
五郎王子を舞った杉田智弥さん(20)、小学校1年から神楽を始められました。
『長刀を扱うのは大変です。今日はステージが広いのでのびのびと舞えますが、まつりなど、人が近い場所はあちこちに気を配りますよ。』
できれば近くで、長刀の起こす風や音を感じてみたい舞です。
〇流れ〇
亡き父、盤醐天王の領地を持つ4人の兄弟王子に対して、自分の領地を求めた五郎王子が、一人で多勢と戦うために必死で武者修行をする様子を舞います。











2018,04,03 Tue 15:15

新入社員の皆さんの初々しい姿を拝見しました。
白シャツ、スーツに、新しいカバン。
加えて緊張気味な面持ち。
今日は、どんないちにちだったでしょうか。
平和公園では、ブルーシートを守る新人さんたちの場所取りの景色をいくつか見ました。
《花見と新入社員》これぞ日本の伝統と感じます
「第4回 十二神祇神楽大会」からご紹介します。
この大会では、広域十二神祇神楽連絡協議会の下前富男会長が、要所要所に十二神祇神楽の歴史や演目の見方などを解説されるので。
もう!大きな鱗が目からぽろぽろです。
その中に、“所作”と“型”は違うもの、というお話があってビクッとなりました。
『えっ?違うんですか??』と
これまでブログにいっぱいいい加減なこと書いていたのでは
ざっくり分けると。
型は神前・儀式として、しなければならない決まり事。
所作はそれに伴ってくるもの。
という大きな捉え方が出来るようです。
しかし、これも又、考え方に色々あると補足されます。
私の中では、ぼんやりとしかまだ振り分け出来ないので、もっと理解しないとここではまとめることができません。
でも、聞いて答えてくださる方がいるというのは、本当に嬉しく心強いことだと思います
~第七幕 灑水(しゃすい)河津原神楽団~
第二幕の浅原神楽団は「社水(しゃすい)」と表記されます。
河津原神楽団でも社水とされていたようですが。
先輩方から「捨水(しゃすい)」「灑水(しゃすい)」という表記もあると伝えらていたそうです。
灑水とは“さらさらした水(清らかで濁りの無い水)を注ぐ”という意味があると伺いました。
命を育み、時に、奪う水を畏れ敬い、神と繋がる舞かなと想像します。
又、この灑水の厳粛で優雅な舞も、神の前で謙虚であった古来の人々の姿を感じさせます。
〇流れ〇
この舞は4人の大夫が舞う神祓舞で、一間四方(畳2枚敷)の中でまうことを定式としています。
舞振りとしては、「順逆」「座替わり」「はいとう」「よなれ」「座がため」等、弊舞の所作が全て含まれる基本の舞です。
弊・和鈴・扇を用いて、太鼓・鉦・笛が奏でる五調子に合わせる4人の大夫の優雅な舞振りと和歌朗詠を鑑賞して頂きたいと思います。







2018,04,02 Mon 21:59
桜吹雪に混じって、花がまるごとポタリポタリと降ってくることがあります。
不思議に思うでしょうが、その犯人は、この子たちです。

桜の花の蜜が好きなスズメの“盗蜜行動”と言います。
蜜を吸うのはスズメばかりではありませんが。
メジロなどの細いくちばしと違って、スズメの太く短いくちばしでは上手に蜜を吸えません。
そこでスズメは、花を根元からちぎって、裏のがく側から吸い取るのです。
人は桜の下でお花見。
スズメは桜の中でお食事。
お天気が続いて桜が長持ちしてほしいのは、人だけじゃありませんね

すっごい演目に出会いました
~第六幕 きつね 五日市芸能保存会~
玉藻前系ではありません。先にあらすじと流れをどうぞ。
〇流れ〇
この舞はとても楽しいひょうきんな舞です。
六郎が畑で種まきをしていると子ぎつねが現れて、種を食べたり投げ捨てたりします。六郎は怒って鍬を振り回して追い払いますが、狐は負けじと六郎に臭いおならを吹きかけ騙します。
六郎はその臭さに我を忘れ、狐のなすままに踊り始めます。
今では継承されている団体が数えるほどしかないという、貴重な演目です。
まつりの中で、舞子さんが氏子さんや大衆の中に紛れ、皆で楽しく過ごす温かみのある様子が浮かぶようです。
昔から“人を化かす”という狐の身近さや神秘も感じますね。
今回、可愛く表情豊かな狐を舞った竹本応(あたる)君(もうすぐ5年生)と、六郎を舞った章(あきら)さんは親子共演でした。
これ以上ないチームワーク!と思ったのですが『息子もそろそろ体が大きく重たくなってきたので次を育てないと・・』ということでした。
応くんがお父さんの年頃になる時代にも、このイタズラ狐が変わらず愛され、舞い続けていますように。









2018,04,01 Sun 20:01