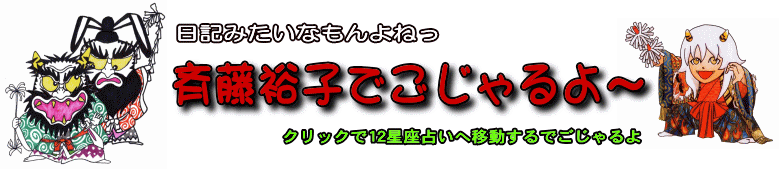長尾良文団長です。
「江戸時代の中期。現在の島根県邑智郡羽須美村の神職から、梶矢の住民数人が神職神楽を習い、氏子神楽を舞うようになりました。。。」
これが全ての始まり、梶矢神楽団が安芸高田の神楽文化の元祖と呼ばれる所以です。
この長い間にどれくらいの人々が継承者として、梶矢の舞を伝え発展させてきたか、私には想像もできませんが。
この日の舞台に繋がっているんだな~と感じます。
又、古典演目の伝承を柱に挙げられる一方で、神楽はそれだけでは面白くないとお話される柔らかさが、大きな魅力です。
梶矢弁とユーモアいっぱいに続きます。
『私らぁ久しぶりにこんな町の真ん中に出てきまして。2日も3日も前からドキドキしましての、遠足のような気持ち言うんですかの。。。』
団長さんに就任されて半年、お忙しいでしょう?
『体型を観てもらえりゃあ分かりますが、ストレス太りでしょうの
楽しいお話を、ありがとうございました!
7月19日(日)第1回 広島土砂災害復興支援チャリティー神楽。
翌20日(祝・月)は湯治村神楽ドーム・昼公演に出演です。

~第二幕 塵倫~
梶矢の先輩方からの言い伝えによりますと。
空飛ぶ塵倫を射抜いた「神変不思議な弓矢」の弓矢とは“官と民”を表す説があるそうです。
弓と矢、どちらが官でどちらが民とは不明ですが。
なんでも一緒にやらにゃ~ダメなんだという訓えが含まれるのではと、お話がありました。
塵倫と塵輪。“輪”という字もしっくりきますねぇ。。。。
(※写真がちょっと・・・思うように撮れませんでしたが、雰囲気だけでもどうぞ。)

大太鼓:上田正幸さん、小太鼓:徳物一則さん、
手打鉦:柴野利成さん、笛:神田光太郎さん。





塵倫で使用されるこの面は、もう定かではありませんが、明治のころの面と思われます。
張り子の面で、頑丈。修理もほぼしていないそうです。
・・・それにしても「鬼の手」って難しいですねっ

2015,07,08 Wed 13:11