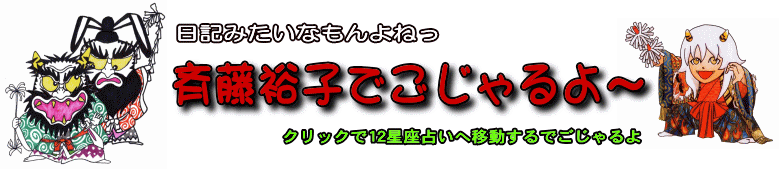寒さがぶり返しました。
ほころんだ梅の蕾も、雨の冷たさにキュッとなっているように見えます。
毎年この頃、上関の城山歴史公園の河津桜を見に行きます。
約190本の河津桜、4000球の水仙、そして大きく広がる瀬戸内海。
例年ならもう満開を過ぎて、桜吹雪に息を飲む景色となるところ。
今年はまだ1~2分咲きなのだそうです。
今週末くらいが見ごろかも。
近くの上関の道の駅も面白くて、ドライブにおススメ。
上関観光協会
https://www.kaminoseki-kanko.jp/?p=2938

心の中で“やったぁ
~鈴張神楽団「桝屋お蓮 」5月1日~
《この神楽では夫に裏切られた女の抑えがたい愛憎を舞いますが、復讐を果たして尚悲しく、神にすがるお蓮の心を感じてください。
又、物語性豊かな中に、女性から“その半分が鬼”となり、ついに鬼となって最後は蛇体となっていく、広島神楽の面白さのひとつ・面の早変わり舞の技術にもご注目ください。
この演目では、神楽笛ではなく、音階をしっかり表現できる篠笛を用いています。》
大太鼓:橋原槙也さん、小太鼓:橋原義則さん、
手打鉦:大本 彩さん、笛:木村千里さん。
桝屋お蓮:竹迫正棋さん、枡屋久兵門:山中数人さん、
鍛冶屋抜刀斎:山中伊吹さん、事代主命:石川昌士さん。
〇鈴張神楽団の皆様の2025年の出演は、10月22日(水)です。
2025,03,03 Mon 23:06
ご署名をありがとうございました。
2月末に間に合うように、送らせて貰いました。
全部で537名の方の署名が集まりました。
3週間の中で、多くの方にご協力を頂けたのは。
お声がけをした方の中に「自分も署名を集める!」と、一緒に活動して下さった方が複数名いらっしゃったからです。
<(_ _)>アリガトウ
署名活動は初めての事で、はじめのうちオロオロしてしまいましたが。
賛同の気持ちや体験を聞かせて下さる方もいて、一人でも多く署名してもらおうと前向きになりました。
全国から集まるこの署名は、動物環境・福祉協会Evaから、環境省 警察庁 消費者庁へ提出されます。
昨今、SNSの普及も手伝って動物虐待の疑いに関する情報は表に出やすくなってきたように感じます。
しかしそれ以上は踏み込めない現状で、いつも命が奪われてから明らかになる。。。の繰り返しです。
しかも、司法の裁きはとても軽い。
動物愛護管理法は、運営されていないも同じ。
日本は動物福祉の後進国だと強く実感します
人間にも動物たちにも優しい国でありますようにと、願いつつ。
悲しいことですが、日本ではもうモラルだけでは命は救えないのかもしれません。
変化可能なところから風穴を開け“命を守る国”を未来へおくりたいものです。
今後も活動に注目していきたいと思います
https://www.eva.or.jp/
2025,03,02 Sun 23:45
全て終わったー
ガンバッタ ٩(ˊᗜˋ*)و ガンバッタ~
ので、これからゆっくりウサギ吸います♪
特に耳と耳の間~
25回目の今年はグランプリ大会です。
第19回~25回までの優勝団体8団体の競演と、特別出演2団体の出演です。
当時の様々な瞬間を思い出して、熱くなりそうですね・・・
改めて競演は、応援する側も力入るし。
そして、怖くて嬉しくていろいろ感情が揺れて、拍手も大きくなります。
2025競演の幕開けの大会でもあります。
分かち合いましょう!!
~春選抜 第25回 吉和神楽競演大会グランプリ~
4月26日(土)廿日市市立吉和小・中学校 体育館
8時30分開場 9時20分開会
プログラム
「四方祓」 堀神楽団
「天の岩戸」栗栖神楽団
「紅葉狩」横田神楽団
「塵倫」堀神楽団
「紅葉狩」大塚神楽団
休憩
特別出演 三谷神楽団「矢旗」
「鐘馗」津浪神楽団
「滝夜叉姫」高井神楽団
「塵倫」吉和神楽団
「葛城山」宮崎神楽団
特別出演 原田神楽団「大江山」
〇チケットについて
前売り券は、席によって電話申し込みや、チケット取り扱い店での購入など異なります。
又、販売期間も異なりますで、チラシやお電話での確認をお願いします。
https://hatsu-navi.jp/event/2022_22thyoshiwakagura/
~電話申し込み~
前方自由席(予約制・エリア内での場所指定は不可)前売券3500円・当日券4000円
はつかいち観光協会0829-31-5656(平日10時~17時)
売り切れ次第終了・3月17日まで販売
~取扱店での購入~
自由席:大人(高校生以上)前売券3000円・当日券3500円、小人(小・中学生)前売り券当日券共に500円
撮影席:前売券・当日券共に別途1000円
☆当日会場受付でお申込み後、撮影許可証とのお引換え
自由席前売券取扱店
ウッドワンさくらぴあ事務室、はつかいち観光協会、吉和ふれあい交流センター、
佐伯商工会、コムズ安佐パーク、中澤商事
4月25日(金)まで販売
※升席完売、前方指定席も僅か。
※ビデオ撮影・カメラ撮影は撮影席以外では禁止。申し込み(別途1000円)が必要です。
※会場受付は、席種によって場所が異なります。
※会場敷地内立ち入り・駐車は当日朝7時からです。場所取りはできません。
問:廿日市観光協会吉和支部 0829-77-2404
吉和ふれあい交流センター 0829-77-2116


2025,03,01 Sat 23:21
間に合わないかと思ったー
本日分だけは!先程、やっとこさ一段落しました
一日中苦手なエクセルと戦っていたので、目が小さくなりました。
。。。言うてねっ!早く取り掛かれば良いものをギリギリにするからなんだけどね。。。
この大仕事終わったら、確定申告もしなきゃだわ。
おしりに火傷しないうちに。
明日は2月最終日、楽しい日にしましょうね
ルリビタキ、まもなく北帰行。
吉田神楽団の皆様の土蜘蛛をご覧頂きました。
県民文化センターのロビーは、早くから賑わっていて。
スタッフの皆さんも神楽ファンの皆さんも、にこにこ神楽談議
神楽の大きなエネルギーに包まれておりました。
ところで。
上演後の撮影会に、突然登場した「破車(やぶれぐるま)」さん。
ご存知・吉田神楽団オリジナル演目「六条」に登場する悪なのですが。
この破車さんこそが、六条御息所を狂わせた元凶でしょうから。
色々気になっちゃって。
この面への拘りも、聞けば聞くほど。。。別機会にお話させて頂ければ嬉しいです

吉田神楽団の、優美な奏楽と舞にはじまり。
大鬼のダイナミックな舞で結ばれる。
“演出で魅せる”とは異なる、土蜘蛛でした。
しっっっかり味あわせて頂きました。
吉田神楽団 土蜘蛛
《最後に登場する土蜘蛛の精魂の面は、およそ50年前に作られ先輩方が使われてきた面を5~6年前に復元したものです。
何とも言えない恐ろしさと表情を持ち、我々の先輩方の想いが宿る面です。我々の先輩方の志を受け継ぐと共に、現団員皆の自慢の鬼面でもあります。》
大太鼓:松田 淳さん、小太鼓:橋本創太さん、
手打鉦:藤原 佑さん、笛:橋本千尋さん。
源頼光:岡本充行さん、卜部季武:藤野克洋さん、
坂田金時:升田 亮さん、胡蝶:内藤憲幸さん、
土蜘蛛の精魂:西岡保明さん。
吉田神楽団の皆さんが「神降し」「滝夜叉姫」で出演されます

2025,02,27 Thu 22:05
お出掛け前に、2024ひろしま神楽定期公演4月から。
今日も“見所”を、一緒にご紹介します。
写真が多くなっちゃったので、タテに長いですよー。
ではでは後ほど、県民文化センターでお会いしましょう✨
~吉和神楽団「八岐大蛇」4月17日~
《秋祭りの最後を飾ることが多い、花形演目。
酒に酔った大蛇たちの鮮やかなフォーメーションをご覧ください。
複雑に蛇胴を組んでいく“縄”など、大技が続きます。
大蛇のリーダーと須佐乃命の真剣勝負には、皆様の拍手とご声援をお願いいたします!》
大太鼓:鈴政憲雄さん、小太鼓:山崎翔太さん、
手打鉦:研谷浩樹さん、笛:佐藤信治さん。
須佐乃命:山本博之さん、足名椎:山崎英治さん、
手名椎:冨野虎之丞さん、櫛稲田姫:深野憲司さん、
大蛇1:山本正也さん、大蛇2:齋藤拓也さん、
大蛇3:小田真也さん、大蛇4:真田健太さん、
大蛇5:齋藤勝也さん、大蛇6:小田 真さん。
〇吉和神楽団の皆様の2025年の出演は、4月23日(水)です。
~阿刀神楽団「鬼退治の舞」「八つ花の舞」4月24日~
「鬼退治の舞」
《神社の秋祭りでも抜群の人気ある神楽です。
世の中の悪を象徴する3匹の鬼ですが、それぞれに表情・感情豊かに舞われます。》
太鼓:瀬川一之さん、手打鉦:瀬川萌乃香さん、
笛:若田佳子さん・野稲亜耶子さん。
杵築:大坪裕昭さん、大鬼:小西晃紘さん、
中鬼:瀬川雄一さん、小鬼:小西野々花さん。
※写真は全て写真は全てtacobocoさん。有難うございます





「八つ花の舞」
《天蓋にお迎えする神様たちが、この舞を上からご覧になった時、花のように開いたり閉じたりするように見えるので“八つ花の舞” 。日本全国の神楽団体でも八つ花の舞を保持する団体は少なく、阿刀神楽団の代表演目。刀を持った後のアクロバティックな舞は、一緒に緊張感を味わってください。》
太鼓:瀬川一之さん、手打鉦:瀬川雄一さん、
笛:小西茉麻さん・野稲亜耶子さん。
太郎:栗栖隆史さん、次郎:今田 新さん、
三郎:浜広直樹さん、四郎:谷川 輝さん。

〇阿刀神楽団の皆様の2025年の出演は、9月3日(水)です。
2025,02,26 Wed 10:33