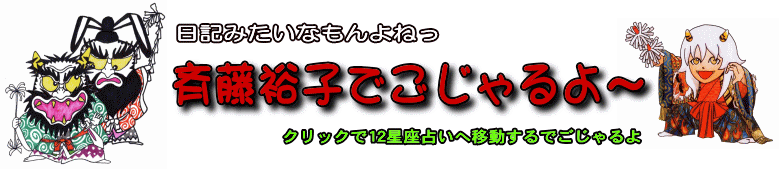大谷選手であったまっています
ツーランホームランを東京ドームで見られた方が羨ましいっ。
天は二物を与えずと言いますが。
大谷さんは心掛けと努力で、自ら二物にも三物にも成しておられてその姿が眩しい。
それにしても、阪神ファンの皆様は熱い週末でしたね。
メジャー球団に連続完封だって。
特に才気浩人投手は明言通り、大谷選手へのリベンジを果たして凄い!
マツダスタジアムの阪神ファンは、少し怖いイメージなんだけど。。。
黒と黄色の組み合わせが怖いし、特攻服も怖い(しっぽ付きは可愛い)。
世界が相手になると、頼もしいですね
吉田神楽団のエネルギーマンスとなる、8月。
そして、殺生石を撮っている最中、カメラが壊れちゃった阿坂神楽団の皆さま。
今夜はドドーンの2団体のご紹介です。
~吉田神楽団「滝夜叉姫」 8月7日~
《この神楽は、吉田神楽団結成以来、特に力を注いできた演目で、若い団員は舞や奏楽から神楽人としての技を磨いていきます。
沢山ある見せ場の中で、やはり姫から鬼、やがて悪鬼となっていく五月姫の悲しい運命の舞を場面、又この時の面の早変わりにご注目ください。
そして滝夜叉姫の心情に寄り添う奏楽にも耳を傾けてください。》
大太鼓:波多野八朗さん、さん、小太鼓:石川聖也さん、
手打鉦:岡本悠希さん、笛:升田美香さん。
五月姫(滝夜叉姫):内藤憲幸さん、大宅中将光圀:岡本充行さん、
山城光成:藤野克洋さん、夜叉丸:西岡隆典さん。
蜘蛛丸:松田 淳さん。
〇吉田神楽団の皆様の2025年の出演は8月20日(水)です。
~阿坂神楽団「殺生石」8月14日~
《狐の出てくる演目は賑やかで、子供から大人まで人気があります。
悪狐のお話は、(括り方の違いもありますが)大きく分けて3つの演目に分けて舞われています。
殺生石は最終話となりますが、この演目を保持している神楽団は多くはありません。
阿坂神楽団は殺生石を得意演目としており、競演大会の優勝演目でもあります。
今日は、面の早替えを見逃さないように!
又、毒を吐く殺生石を神楽の中でどう表現するかをお楽しみください。》
大太鼓:藤田丈二さん、小太鼓:藤田美幸さん、
手打鉦:上野昭文さん、笛:栗末あいりさん。
玄翁和尚:河野遥人さん、飛び介・狐:河野翔紀さん、
玉藻前:浅枝 匡さん、狐:益井保信さん。
※写真はtacoboocoさん。有難うございます☆











〇阿坂神楽団の皆様の2025年の出演は4月30日(水)「羅生門」です。
2025,03,16 Sun 22:40
早く帰宅して、ゆっくりしようと思っていましたが。
帰宅した途端、冷蔵庫掃除の神様が降臨され。
冷蔵庫と冷凍庫をピッカピカに磨き上げること3時間。。。
爽快感と充実感、半端なかったです。
我ながら頑張ったなぁ エライエライ ( ˘ω˘ )ヾ ヨシヨシ
広くなった冷蔵&冷凍庫を眺めながらコーヒー。
すると。
なんとこのタイミングで宅配便さんが来られ、このような贈り物が。

生のあかてん。
浜田名物・あかてんの、まだ揚げてない冷凍タイプです。
家で揚げたてアッツアツを食べられるってわけです。
早速小分けにして冷凍しておきました。
広くなった冷凍庫に、余裕で美しく並びました。
掃除すると良い事起きるって本当だね
山本蒲鉾店↓ここは甘みのある手打ながてんも、とても美味しいです。
https://yamamoto-kamaboko.com/item/
初めて会いました、戸谷さんちの大蛇さんです。
~戸谷神楽団「八岐大蛇」7月31日~
《戸谷神楽団では以前はゆったりとした六調子でこの神楽を舞っていましたが、近年派手やかさのある八調子で舞っています。
この軽快な八調子に息を合わせて魅せる、活き活きとした大蛇の舞をご覧ください。
今日の手打鉦・40歳の水野君は今日が初舞台で少々緊張しています。
この舞台をきっかけに顔を覚えて頂き、末永くご声援ください。
神楽は何時からでも始められます。
皆様一緒に神楽を舞いませんか?》
大太鼓:奥迫光洋さん、小太鼓:上田壱都さん、
手打鉦:水野隆滋さん、笛:吉野剛二さん。
須佐之男命:若狭義文さん、足名椎:沖野敦史さん、
手名椎:上田晃平さん、奇稲田姫:水野功樹さん、
大蛇:山本圭介さん・佐々木賢治さん・上田槙也さん・下田宏大さん。
〇戸谷神楽団の皆様の2025年の出演は7月30日(水)です。
2025,03,15 Sat 23:37
ウサギの機嫌が悪いです ( ᐢ. ̫ .ᐢ )
今日は昼間はメラメラと焦げましたが、夜は寒かった~
でもキレイな満月と一緒に帰ってきました。
今夜はおとめ座の満月。
おとめ座の持つ“癒し”に因み「暮らしと体調を整え、現実を生きる」がメッセージ。
月の光を浴びておくと良さそうですね。
来月4月13日は、うお座で起こる満月。
うお座の持つ“霊力と直感力”に因み「心の声に耳を傾け、現実との折り合いや自己実現に力を注ぐと良い」とあります。
なるほど“星を読む”とはそういうことなのですね
月を見ている静かな時間が、心を浄化してくれるのは確か。
ただ寂しいので毎年3.8cmずつ地球から遠ざかっていくの、やめて貰えないかな。。。
寝る前更新。
2024ひろしま神楽定期公演7月から。
茂田神楽団の皆様ですっ。
~茂田神楽団「滝夜叉姫」7月24日~
《茂田神楽団が滝夜叉姫を舞い始めたのはおよそ8年前ですが、昨年世代交代を迎え気持ち新たに!ますます大切に舞っています。
可憐な姫であった五月姫が、父の復讐を遂げるためついに鬼となる、この情念を舞や口上に感じてください。》
大太鼓:増原英伸さん、小太鼓:佐々木雅美さん、
手打鉦:宮本正和さん、笛:浅井千秋さん。
大宅中将光圀:谷口裕則さん、山城光成:小滝達也さん、
五月姫:渡邉 潤さん、夜叉丸:正光 白さん、
蜘蛛丸:前保昂輝さん。
〇茂田神楽団の皆様の2025年の出演は8月27日(水)です。
2025,03,15 Sat 00:56
ご飯を食べる時間も水を飲む時間もなく、慌ただしく終演となりました。
平日だし、夜も遅いし、普段は片付けを済ませてササっと帰宅するところですが。
めちゃめちゃ喉かわいたっ
アイスクリームが食べたいっ
ということで、スタッフの皆さんと一緒にアイス。
ちょうど時間は、21時前。
その流れでこちら。

このあと長蛇の列となる、やっぱり人気店。

迷ってマンゴー&ナタデココ
その後、みんなお腹が空いてるってことで、くら寿司。
たっぷりアイスクリーム食べたあとに、生魚。
順番も逆だわ
みんな今日、お腹大丈夫だったかな~??

ポケモンボール出てきた。
こうやって、皆で美味しいもの食べてキャッキャッって話している時に、何か素敵な企画が浮かぶかもしれない。
次はどこに行こうかな。
2025,03,13 Thu 19:11

なくてはならない“いつもの景色”なのですね。
数年ぶりに拝見した鈴張神楽団の皆様の「紅葉狩」。
艶麗な姫、引き締まった舞。
ジャパニーズビューティフルに、海外の方の反応は大きく。
場面ごと、役者さんが幕に下がるたびに大きな声援と拍手が送られていました。
素敵なものは素敵。
感動の気持ちは舞台に。
舞台と会場とのキャッチボールを、袖で拝見していて嬉しさ倍増だった
~鈴張神楽団 紅葉狩~
《見所は、平維茂を惑わす3人の姫の艶やかさ。
鬼女舞ならではの、指先から足先までしなやかな魅力的な舞をご覧ください。
又、姫がだんだんと鬼へと変わっていく面の早変わりは必見です。
そして、4人の奏楽者と一体感ある激しい合戦の場面では、皆様ぜひ拍手で一緒に舞台を作ってください。》
大太鼓:橋原槙也さん、小太鼓:大田拓也さん、
手打鉦:大本 彩さん、笛:木村千里さん。
平維茂:山中数人さん、従者:沖野末昇さん、
紅葉:竹迫正棋さん、菖蒲:吉田和哉さん、
桔梗:山中伊吹さん、八幡大菩薩:藪本 司さん。
次回特別公演は、3月26日(水)琴庄神楽団の皆様の「滝夜叉姫」です。
(チケットぴあの前売り指定席は完売です)
2025,03,13 Thu 18:15